Dr. Dre (ドクター・ドレー)の「The Next Episode」は、Snoop Dogg (スヌープ・ドッグ)らとの黄金コンビが放った西海岸ヒップホップ史上最大のアンセムである。イントロ一音で現場をロックするこの曲の凄さは、David McCallum (デヴィッド・マッカラム)の「The Edge」を元ネタにした重厚なビートと、あまりに有名な「あの幕引き」のフレーズにある。2分41秒という短さに西海岸の美学が凝縮された、まさに時代を超越した一曲だ。
🎧 クイック概要:10秒でわかる基本データ
| アーティスト / 曲名 | Dr. Dre feat. Snoop Dogg, Kurupt & Nate Dogg – The Next Episode |
| 収録アルバム | 2001 (1999) |
| サンプリング元 | David McCallum – The Edge (1967) |
デヴィッド・アクセルロッドの「哀愁」を「最強の重低音」へ
この楽曲の心臓部は、Dr. DreとAftermath所属のプロデューサー、Mel-Manによる共同プロデュースで生み出された。核となっているのは、1967年に録音されたDavid McCallumの楽曲「The Edge」だ。
この曲のプロデューサーであるデヴィッド・アクセルロッドが作り上げた、緊張感あふれる独特のリフ。Dreはこれを巧みに抜き出し、特有のクリーンかつ重厚なプロダクションで磨き上げた。アッパーでありながら、胃に響くようなヘビーなビート感。この「サンプリングの妙」こそが、四半世紀経っても色褪せない強度の正体である。
6年越しに結実した「幻のエピソード」

ファンにとって興味深いのは、この曲には「前日譚」があるという点だ。実は、スヌープ・ドッグの1993年の伝説的デビュー作『Doggystyle』に、「Tha Next Episode」という同名のコラボ曲が収録される予定だった。
しかし当時はサンプル音源の許可が下りず、あえなくお蔵入り。その時使われるはずだったビートは、後にWarren Gの楽曲「Runnin’ Wit No Breaks」として世に出ることになる。時を経て1999年、アルバム『2001』でようやく結実した本曲は、文字通り二人の「次のエピソード」を待ち望んでいた世界中のファンへの、これ以上ない回答となったのだ。
伝説の2分41秒:計算し尽くされた構成とフック
アルバム『2001』は、一枚の映画のような構成を意識して作られている。その中で「The Next Episode」は、わずか2分41秒(LPバージョン)という潔い短さだ。この短い尺にエネルギーを凝縮させることで、聴き手に強烈なインパクトを残している。
リリックは西海岸のギャングスタ・ラップやパーティー・アンセムの王道をいくスタイルだが、この曲を不滅にしたのは、今は亡きネイト・ドッグ(Nate Dogg)によるソウルフルなフックだ。特に、曲の最後を締めくくる「Smoke weed every day」というラインは、今やヒップホップ・カルチャーのアイコン。インターネット・ミームとしても拡散され続け、ジャンルを超えた認知度を誇っている。
商業的成功と、今なお「大舞台」で鳴り響く理由

セールス面でも圧倒的だった。全米チャート23位、全英3位を記録し、アルバム『2001』のマルチプラチナ・ヒットを牽引。アイス・キューブやエグジビットがカメオ出演した豪華なミュージックビデオも、その勢いを加速させた。
さらに、この曲の凄みは「現在進行形」であることだ。
- 2022年: スーパーボウルLVIのハーフタイムショーでオープニングを飾る。
- 2024年: パリオリンピック閉会式(LA28への引き継ぎセレモニー)でも、ロサンゼルスのビーチから世界へ向けて披露。
曲名が示す通り、「次の大舞台(Next Episode)」を象徴するアンセムとして、今もなおカルチャーの最前線に君臨している。圧倒的なブランド力、時代に左右されないプロダクション、そして一度聴いたら忘れられないフック。これらすべてが完璧に噛み合った、まさに奇跡の一曲である。
関連記事はこちら

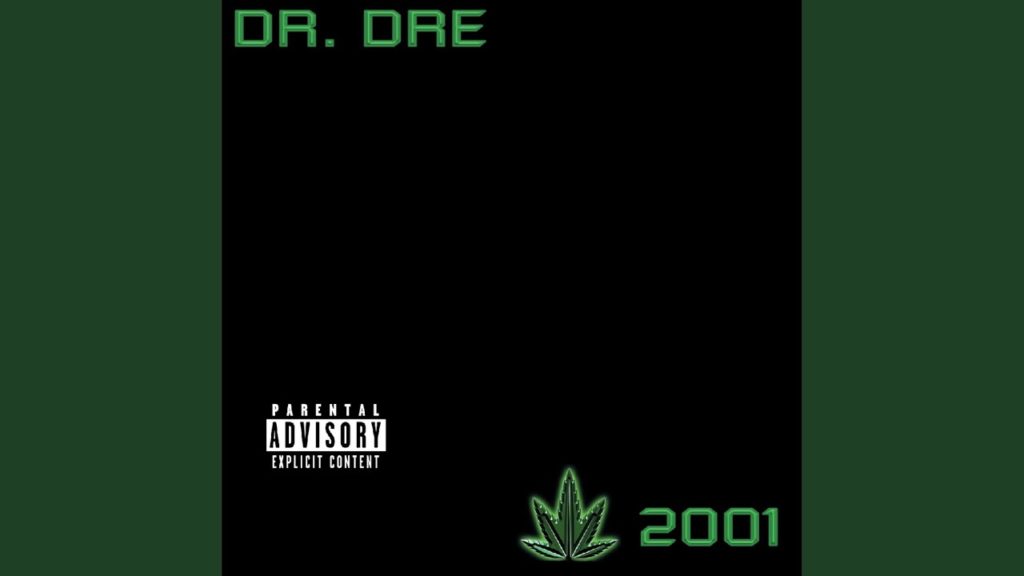



コメント